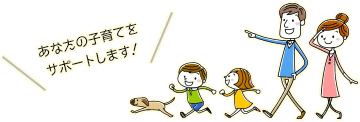清瀬の里親夫婦が語る、共に歩む喜び
インタビュー
里親という人生を選択した市内在住ご夫婦。里親登録前から現在高校生になるA君と暮らし始めて1年が経過した現在の様子までを語っていただきました。
里親になろうと思ったきっかけは何ですか?
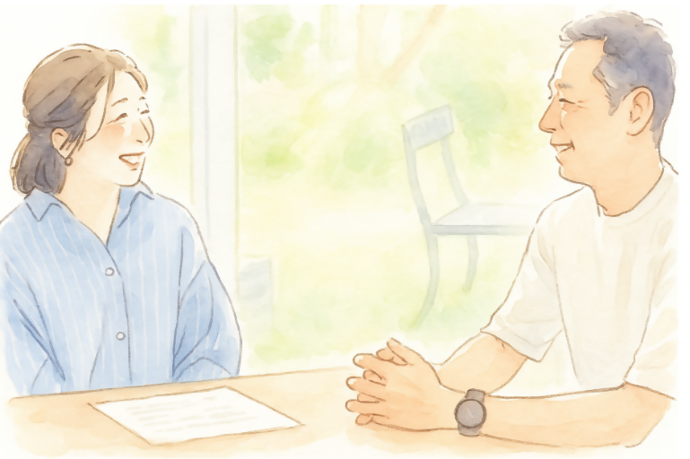
インタビュアー(以下、イ):里親になろうと思ったきっかけは何ですか?
里母: 実姉が15、6年前から里親をしていて「里親というカタチもいいな」と結婚前から考えていて、結婚して子どもを授からなければ、里親をしたいという思いは強くありました。
里父: 私は、妻の姉が里子の子どもたちと接しているのを見て、「楽しそうだな」と感じていました。
イ: 清瀬市にお住まいになってから、里親を始められたそうですね。
里母: はい。清瀬に転居した1ヶ月後には、児童相談所に連絡していました。
実際に里親になるまではどうでしたか?
イ: 実際に里親になるまではどうでしたか?
里母: 研修が多いと感じました。登録前研修や乳児委託研修など、多岐にわたる内容でした。でも、どんな子が来るか分からないから、全部受けることで「安心材料」になりました。
イ: 里親登録後、子どもを迎えるまでの半年間、どのように過ごされましたか?
里母: 「夫婦二人きりの最後の生活」と思い、ご飯を食べに出かけたり飲みに二人で行ったりと、夫婦二人だけの時間を大切に過ごしました。
A君との生活はいかがですか?
イ:A君との生活はいかがですか?
里母: A君が家に来た当初、新たな環境に来て不安な様子が3ヶ月ほど続いていました。日々、私たちは「大変だよね」「自分だけじゃないよ」と共感し、そばに寄り添い続けました。
里父: A君は施設にいたということもあり、当初は家で一人で過ごしたり、出かけるのも難しかったのですが、今では一人で買い物に出かけ、自転車に乗ったり、自発的に料理や掃除をしたりと、目に見えて成長していく姿に感動しています。
里母: また最近では、電車の乗り方や交通マナーも身につけ、片道1時間半かけての高校への通学も全く問題ありません。
A君の学校での様子はどうですか?
イ: A君の学校での様子はどうですか?
里母: 学校に慣れて友達ができてから、徐々に落ち着いてきました。家に友達を連れてくるようになり、「大変なのは自分だけじゃないんだ」と気づいたことで、精神的に安定したようです。高校では陸上部で長距離に取り組んだり、パソコンのタイピング練習、と様々なことに意欲的に挑戦しています。
里親になって良かったと感じる瞬間は?

イ: 里親になって良かったと感じる瞬間は?
里母: 運動会や、中学校の卒業式では感動して思わず泣いてしまいました。授業参観では成長した姿を見たりと「子どもがいなかったら経験できなかったこと」だと感じます。A君のおかげで多くの喜びを経験させてもらっています。
里親家庭を取り巻く社会や会社の理解についてはいかがですか?
イ: 里親家庭を取り巻く社会や会社の理解についてはいかがですか?
里母: 私の会社では実子ではなく、里子だからという理由で育児時短勤務が認められず、モヤモヤしました。社会全体で里親制度への理解はまだ不足していると感じます。
清瀬市での子育てはいかがでしょうか?
イ: 清瀬市での子育てはいかがでしょうか?
里母: 放課後等デイサービスや、病院も多く子どもが体調不良の際もすぐに診てもらえるので安心です。A君が学校を転入する際は中学校の先生方が、特別に時間を割いて配慮してくれる機会もあり、とても親切でした。
里親を考えている方へメッセージをお願いします。
イ: 里親を考えている方へメッセージをお願いします。
里母: 興味があったら、すぐに児童相談所へ。まずは話を聞きに行くのが一番です。もしかしたら、「子どもと関係を築けるだろうか」と不安があるかもしれません。でも、それは時間と生活の中で培われるものだと思います。勇気を出して一歩踏み出してほしいです。
里父: 大変なこともありますが、子どもの成長を間近で見られる喜びは何物にも代えがたいです。ぜひ、新しい家族のカタチを清瀬で育んでほしいと願っています。
里親の現状と課題
「家庭で育まれる環境が必要な子ども」 がいるという現実
親の病気や離婚、虐待、経済的な理由などによって家族と離れて暮らしている子どもが全国には約42,000人、東京都には約4,000人います。児童養護施設や乳児院で生活している子どもの中には、あたたかい家庭環境を必要としている子どもたちがいます。里親家庭で特定の大人との愛着形成や信頼感、安心感を育み、子どもたちは健やかに成長することができます。
認知拡大と正しい情報普及、 里親登録数と委託の推進
養子縁組と混同されていたり、経済的な負担に対する誤ったイメージがあったり、多くの世帯が里親になることを躊躇する現状が解決されないままになっています。すべての子どもに健やかな生育環境を等しく提供するには、里親制度に対して広く認知を拡大すること、そして、正しい情報を普及するとともに、里親登録を増やしていく大きな課題があります。
里親Q&A
Q:特別な資格は必要?
A:里親になるには、子どもの養育について理解・愛情・熱意があり、子どもの養育に適した環境があるなどの要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。保護を必要とする子どもに寄り添い、あたたかい愛情と正しい理解をもって接することができれば大丈夫です。
Q:里親に経済的な負担はありますか?
A:子どもにかかる必要な養育費や医療費は東京都から支給されます。
※里親の種類や子どもの年齢によって支給額は異なります。
Q:共働きでも大丈夫?
A:基本的に問題ありません。子どもの養育に支障がでないよう調整が必要なこともあります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭支援センター子ども家庭支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター2階
電話番号(直通):042-495-7701
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。