きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <結城昌治 2. 波郷に出会い俳句にはまる>

![]()
B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)
結城昌治 2. 波郷に出会い俳句にはまる
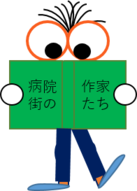
B 結城さんが入った清瀬の療養所は、東京療養所、だったよね。
O そう。昭和14年(1939)に傷痍軍人東京療養所として始まった療養所で、終戦の年、昭和20年12月に国立東京療養所となる。
B 福永武彦や石田波郷といっしょだったんだよね。
O よく覚えていたね。療養所のようすを結城の言葉で見てみよう。
私が入った部屋は南七寮五番室の窓際で、差額ベッドなどはなく、向かい合いにベッドが三台ずつ並んだ六人部屋です。隣の六番室に石田波郷、八番室に福永武彦がいました。(略)薬がなくて大気安静が第一という時代ですから、真冬でも窓を開けっ放しで、もちろん暖房も冷房もありません。
(『俳句つれづれ草』)
B ひゅう、真冬も開けっ放し! 寒すぎでしょ。 ところで、「四」がつく病棟や病室って、ほんとになかったんだね。吉行淳之介がいた清瀬病院とは、違うねぇ。東京療養所で、結城さんの毎日は、どんなふうだったの?
O 結城自身の回想では、こんな感じだ。
(『死もまた愉し』)
B 安静時間! 病院街が静まり返る時間だね。規則正しい生活をしてたんだね。
O 食事のことも書いているよ。
(『俳句つれづれ草』)

B 食べ物の好き嫌いって、ぼく、あんまりない方だけど、でもなぁ、このメニューの繰り返しだと、うーん、ちょっと辛いかも。それに、夕食が午後5時って、早くない?
O そうだね。でも、夕食後の時間は、比較的自由に過ごせたらしく、囲碁や将棋くらいではつぶしきれないたっぷりの時間に、それぞれにいろんなことをしたようだよ。詩や短歌や俳句を詠んで仲間と冊子にまとめたり、なかにはキリスト教の布教や、共産党の宣伝をする人もいたそうだ。
B そっかぁ、文学サークルの同人誌は、時間たっぷりの療養所の生活から生まれたんだね。
O 療養所には、たっぷりの時間と、それから、刺激的な出会いがあったんだ。結城が東京療養所に入ったとき、隣の部屋にいたのが、俳句の石田波郷だ。
(『俳句つれづれ草』)
B うっひゃぁ、いきなりレベル高いね!結城は見よう見まねで俳句を始めたんでしょ?
O そう。波郷が生死の境にある想いを詠む姿を間近にみて、たったの17文字でこれだけのものを表現するなんて、すごい人だと思いはじめる。
B めちゃめちゃ刺激的な出会いだね!
O そして、結城は自分でも俳句をつくりはじめるんだ。
B 生死の境にあって詠んだ波郷さんの俳句って、『惜命』の句だね。
O キュイ~キュイ~その通~り。句集『惜命』は、療養俳句の金字塔ともいわれている。その大家のすぐそばにいて、結城も俳句に傾倒していくんだ。そして『松濤(しょうとう)』にも投句するようになる。
B しょうとう?
O あれ? 石田波郷を紹介したときに話したと思ったけど、覚えてないかな。『松濤』は東京療養所に古くからある句誌だ。
B あ、思い出した! 電気消すんじゃなくてね。しょうとう。
O 俳句の波郷の入所を受けて『松濤』には前からあった瀧春一の選と並んで石田波郷選も設けられて、投句のなかから瀧と波郷が選ぶ句がそれぞれの選として掲載されたんだ。
(『俳句は下手でかまわない』)
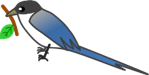
B 広く、深く人生とかかわる俳句の一ジャンルかぁ。ズーンとくるね。療養者にとっての俳句は、病気と向き合う日々の支えだったんだね。
O それはまさしく、生と死に向きあう日々でもあったからね。俳句だけじゃなくて、結城は波郷と出会って、死生観にも影響を受ける。
(『俳句つれづれ草』)
B こうもう?
O 鴻毛(こうもう)は、鳥の羽のこと。軽いもののたとえだ。死はそれよりもっと軽いと覚悟せよ、と言われたわけだ。
B 結城さんは、国のために死のうと考えて海軍に志願したんだったよね。でも、死ぬっていうことが実感としてわかっていなかったからこその志願で、わかっていたら志願なんかしなかった、とも言ってたね。
結核になって、東京療養所に来て、波郷さんの言葉を聞いて目が覚めたんだね。

O 療養所に入るときだって、生命への執着よりも、心配してくれる母親から離れたい気持ちのほうが強かった、という結城だけれど、療養所で死と隣り合わせのような毎日を送るうちに、あらためて生きたいと願うようになった、と言っている。
B それは、波郷さんの影響も大きいね、きっと。
O 結城は昭和54年(1979)に『歳月』という句集を出しているんだ。その「序」にこんなことを書いているよ。
ところが、俳句と縁を切って二十数年も経ってから作意がよみがへつてきて、昨年の一月から仲間をつのつて句会を催すやうになつた。「くちなし句会」といふもつともらしい名までつけて、いつたいどういう風向きか自分でも分らないありさまである。かつてのやうにひたむきではないが結構熱心で、毎月一回の句会もすでに一年以上つづいてゐる。若い頃の句に昨年一年間の句を加へて「歳月」と題したが、感無量の思ひである。
(『歳月』)
B 長い時間が経ってからまた俳句を作ろうと思ったとき、きっと清瀬のこと、たくさん、たくさん思い出したに違いないね。
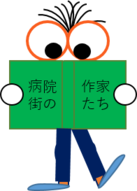
![]()
(書影)
結城昌治『歳月』未来工房 昭和54年(1979)9月
(引用)
結城昌治『死もまた愉し』講談社文庫 2001年12月
結城昌治『俳句つれづれ草ー昭和私史ノート』朝日新聞社 昭和60年(1985)7月
結城昌治『俳句は下手でかまわない』朝日新聞社 1997年4月
結城昌治『歳月』未来工房 昭和54年(1979)9月
![]()
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【郷 静子(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【結城昌治(東京療養所)編】
![]()
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
