きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩<石田波郷 4. 故郷のごとき療養所>

![]()
石田波郷 4. 故郷のごとき療養所
B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)

O 波郷の東京療養所生活は、昭和23年(1948)5月に始まり、25年(1950)2月退所で一区切りつく。退所を前に25年の正月を、波郷は久しぶりに自宅で過ごすんだ。そのときのことも『清瀬村』に出てくる。外泊許可をもらって、清瀬駅に向かう。
(「正月」)
江東は砂町の自宅で、波郷は楽しく家族と過ごす。隣からカメラを借りて子供たちを写したり、凧揚げをしたりもした。そして。
「こここそ、わが住むべき所だ」
と、しみじみ感じた。
(「正月」)
B うーーん。なんて言ったらいいんだろう。せっかく家族と楽しく新年を迎えたっていうのに、ね。清瀬の療養所は、去りがたい思いを抱かせる場所になっていたんだね。
O 福永武彦の足掛け7年に比べれば短いが、それでも2年弱を、生と死を見つめて過ごした場所だからね。波郷は退所後も、清瀬に足を運んでは懐かしの療友との語らいを楽しんだんだよ。「松濤(しょうとう)」の選句も続けていたしね。
清瀬中学校の校歌を作詞
B 退所してから、体の調子は良かったの?
O 無理をしないで、なんとか保っていたんだね。次の入院までの間に、波郷は清瀬にとって、とても大切な仕事を残してくれているんだよ。清瀬中学校の校歌の作詞だ。
B 校歌の作詞! いいなあ~ でもまた、どうして、そういう話になったの?
O 昭和32年(1957)に清瀬中学校は創立十周年を迎えようとしていたんだが、まだ校歌がなかった。十周年の記念に校歌ができるといいね、という話になる。さて、どなたに作詞をお願いしようか。
B なるほど。それで、それで?
O 清瀬中学校の当時の校長平沼栄一先生は、初代校長で退職後は教育長だった永塚泰蔵先生に相談する。俳句をたしなんでいた永塚先生は、清瀬町役場勤務の中村春芳さんが東京療養所で療養中に句会に参加して波郷を師と仰いでいたことを知っていた。そこで、春芳さんを介して波郷さんのところに作詞をお願いに行ったんだそうだ。ふたりで北砂の波郷先生を訪ねること数回。作曲の期日に間に合うように歌詞は出来上がる。作曲者の渡辺浦人氏が「稀れにみるきれいな詩だ」と感嘆されたという話を聞いて思わず綻んだ永塚先生の顔が印象深く思い出される、と春芳さんは永塚先生の句集に寄せて記している。
B 中村春芳さん! 波郷さんの散歩の話に名前が出てきた人だ。そうなのか、俳句の縁から生まれた校歌なんだね。いいね、いいね!
O 清瀬ゆかりの、教科書に句がのる俳人の作詞だからね。誇らしい校歌が生まれたわけだ。
書簡に見る入退院と病院街の変化
B 清瀬中学校の校歌作詞は次の入院までの間、ってことは、波郷さん、また入院したの?
O 肋骨を切る成形の手術だけでは空洞が埋まらなくて、合成樹脂球を詰める手術をした話を覚えてる? その手術は、埋め込んだ樹脂球が原因で炎症を起こす例が相次いだせいで、あまり長くは行われなかった手術なんだけど、波郷の「胸中の球」は、比較的おとなしくしていたんだね。だけど、とうとう炎症をおこして、取り出す手術のために入院することになる。それが昭和38年(1963)のことだ。
B ということは、25年の退所から10年以上だいじょうぶだったんだね。
O そうだね。38年の入院のときには、病院の名前が変わっていた。波郷や福永がいた「国立東京療養所」と、ブンガくんに最初に声をかけた中央公園の辺りにあった「国立療養所清瀬病院」は、昭和37年(1962)に統合されて「国立療養所東京病院」になる。薬を使っての化学療法が定着して、かつて不治の病といわれた結核は治せる病気になった。新しい患者の入院期間は短くなったし、結核で長く療養する患者も少なくなって、病床には空きが出てきた。その一方で木造の病棟は長い年月の間に老朽化。新しい時代の医療を提供するためには、設備を整えた施設が必要。そんな背景があって、ごく近くにあったふたつの国立療養所は、統合に向かうんだ。より敷地が広かった元東京療養所の側に新しい病棟を建てて、順次患者が移っていく計画だ。統合後もしばらく元の病棟で医療は続いていて、それぞれ国立療養所東京病院の、東療病棟、清瀬病棟といったんだ。
B 「東京病院」っていう名前はそのとき、できたんだね。
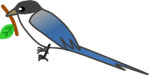
O 石田波郷全集の別巻には、書簡が収められているんだけど、入院ごとに差出の表記をたどっていくと興味深い発見があるよ。
B 最初は、清瀬村の東京療養所南七寮だったよね。
O その通り。二度目のときは、「都下清瀬町東京病院東療北五寮より」なんて書いてある。
B あれ?清瀬「村」じゃなくて?
O 清瀬は昭和29年(1954)4月「町」になっていたんだ。でもね、38年、入院したばかりの手紙には「清瀬村東京病院東療病棟南五寮」とある。思わず筆が動いたのかな。「えごの匂ひがしていかにも療養所にゐるといふ感じがしてゐます」って。最初のときと同じ5月だったからね。このときは、樹脂球を取り出す手術を受けて、同じ年の11月には退院している。
B このときは? まだ続きがあるの?
O 3回目は昭和40年(1965)の4月、呼吸困難で入院。胃の出血による貧血で輸血を受ける。このときは北五寮。6月退院。
B 2か月で退院できたんだね。
O 4回目の入院はその年の12月。呼吸困難のため入院。このとき、東京療養所時代からの療友にあてた手紙には「東京清瀬町東療東三」とある。「東京病院」になってから建てられた新しい病棟だね。「…少々低肺のことを知りました これは どうしようもなく じりじりと終末に押しやられるといった感じがして 不快です 然しそれはそれ なるべく明るく、何事かを為したいと存じます あなたも御元気でよき新年を御迎へ下さい」って。
B 12月入院だと、病院で年越しだったの?
O お正月は外泊許可をもらって自宅で迎えている。年明けにまた病院に戻って呼吸訓練を始めるんだ。松山にいる妹あての手紙では「暖房の個室でまるで避寒にきているやうです 化学療法と呼吸訓練をやり 一人前の仕事もするといふのですから ずいぶん忙しい患者です」と書いている。昭和41年(1966)3月退院する。
B ちょっと長い入院だったんだね。呼吸訓練が必要になったんだ。なんだか苦しそう。
O 41年の7月末には5回目の入院。「清瀬町東京病院東療西三」より結城昌治にあてて「先日は御見舞ありがたう存じました 七寮南の林は小生も近く散歩してみたいと思つてゐます」。この時の入院は短くて10月には退院するんだが、症状が悪化して11月再入院。知人あての手紙で「出たり入ったり忙しい入院生活ですが 病状はいつも同じようなところを上下しています 肺機能低下による呼吸困難、心障害が何かにつけてすぐ起こり そのたび入院といふことになるわけです」と説明している。そして昭和24年以来、久しぶりに新年を病院で迎えるんだ。
B 今度の入院も長かったの?
O 昭和42年(1967)の9月はじめに知人にあてた手紙では「先月末から酸素吸入も全くしなくなり よろづ好調です」「清瀬ももう芒(すすき)がひかり 萩(はぎ)が咲きはじめました 療養所の周囲の もとは畑と雑木林だったところが 住宅で埋まってしまひました 病院も結核病棟をだんだん縮少して綜合病院化するやうです 療養所時代ののんびりさはなくなって 患者を早く廻転させるやうになるのでせう」と語っている。9月末退院。
B よかったね。良くなって。
O ところが、だ。退院からほんの十日ほどで、症状悪化、昭和42年10月、また入院する。翌43年(1968)5月には、自身の東京療養所入所二十周年を、東京病院の病室で迎えている。さらにもうひとつ年を越し、夏を越し、昭和44年(1969)秋、病状険しいなか、妻あき子さんの句集の原稿に目を通して「見舞籠(みまいかご)」という題名を決める。そして師匠である五十崎古郷の句碑のことを気にしながら、11月21日、東京病院で息を引き取る。享年56歳。
故郷のごとき療養所
B 亡くなったのも清瀬の東京病院だったのかぁ。入退院が繰り返されるごとに、つらそうな様子がうかがえるけど、でも、なんていうか、ずっと病気を抱えながら「生きた」っていう感じだなあ。
O この句に、波郷自身の思いが込められているんじゃないかな。
B 「病む生」と清瀬は、切っても切れない縁で結ばれていたんだね。波郷さんは何度もの入退院のあいだに、療養所や病院や、その周りの変化を見てきたんだね。でも、きっと最初の「南七寮」時代が一番印象深いんじゃないかな。なんか、そういう気がする。
O きっと、そうだね。


![]()
(図版)
東京療養所鳥瞰図 国立病院機構東京病院所蔵
(引用)
石田波郷 「正月」『清瀬村』四季社(中央区東銀座) 昭和27年11月
石田波郷 書簡『石田波郷全集 別巻 書簡・雑纂』角川書店 昭和47年5月
石田波郷 「酒中花以後」『石田波郷全集 第三巻 俳句 III 』角川書店 昭和46年6月
石田波郷 「春嵐」『石田波郷全集 第二巻 俳句 II 』角川書店 昭和46年5月
![]()
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
