きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <郷 静子 2. 療養生活の始まり>

![]()
B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)
郷 静子 2. 療養生活の始まり
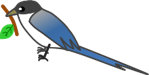
B 戦時中、勤労動員中に同人雑誌を作ってた郷さんは、結核になっちゃったっていう話をこの前聞いたんだよね。
O そう。昭和20年に入って、戦争は激化していくのだけれど、その冬、郷は結核になってしまうんだ。学徒勤労動員での工場労働の時期、無理もあったのかもしれない。なんたって郷は、発病してからも働き続けていたくらいだからね。
B えぇ~~ 病気になっても働き続けるなんて、むちゃくちゃだよ。なんで、そんなことに…。
O そう思うよね。本人の言葉を紹介しよう。
(「古傷」)
「斃れて後已む」っていうのは、死んで初めてやらなくなる、ってこと。つまり、懸命に努力して途中でくじけない!という意味だ。病気でも、しかもそれがすぐに療養が必要な病気であっても、途中でくじけない精神で勤労する、そういうものなのだと思っていたんだね。
B そんなぁ…。今聞くとびっくりしちゃうけど、そのころ、郷さんは言われたことを疑いなく信じてたんだね。ぼくもそのころに高校生だったら、同じように信じたかな。怖いな。
O 空襲で、一瞬のうちに目の前で大切な誰かが死んでしまう経験をする。死は身近にあったんだ。ずっと恐怖の中にいて、無条件に何かを強く信じてしまうってことはあったかもしれないね。
B つ、つらいね。
O 戦争中の経験を、郷は「れくいえむ」という作品に描いている。少女の眼に映った戦争の姿だ。ブンガくんも一度読んでみるといい。
B うん。覚えておくね。
O 空襲による死は辛くも免れた郷だったけれど、戦争が終わったあとは結核に悩まされる。早いうちに適切な処置をしなかったから、良くなったかと思うとまた悪くなって、それを繰り返すうち、病状はどんどん悪化していったんだ。
(「思い出の看護婦さんたち」)
B 自分のことを「オロカな患者」だなんて、突き放して見てるんだね。だけど、良くなったと思ったのにまた悪くなるなんて、結核ってやっかいな病気だね。
O そうなんだ。熱も高くなければ咳がひどいわけでもない、というので、よくなったと自己判断してしまうんだが、結核菌は潜伏中。患者がちょっと無理をして弱ったりしたら、すぐまた勢いを取り戻す。再発、だ。こういう長患いに悩まされたのは郷ひとりではないけれど、彼女は、病状の安定と悪化を繰り返しながら、結核療養所での生活を なんと3度も経験してるんだ。
B えええーーっ、3回も!
O ちなみに、最初の療養所暮らしは、昭和21年8月末から。半年以上も入所許可が出るのを待ったそうだ。
B 待ってる間にどんどん悪くなっちゃいそうじゃない?
O 心配になるよね。そのころ、療養所のベッドが空くのを待ってる人がたくさんいたんだ。入院・入所期間も長かったから、ベッドはなかなか空かないし。一方で、希望者はわんさかいたんだ。だから半年といわず、もっと長く待った人たちもいたんだよ。
B そうなのかぁ。郷さんは半年待ちで入れたんだから、まだよかったのかもね。清瀬にはいつごろ来たの?
O 昭和30年に清瀬の東京療養所で手術を受けている。東京療養所は郷にとって3つめの療養所だった。
B 戦争が終わってやっと平和な生活になるかと思ったら、10年近くも結核で療養なんて、やるせないね。療養生活も辛かったんでしょ?
O もちろん、青春時代を結核とともに過ごしたのは、苦しいことだったに違いない。けれど、それだけでもなかったようだよ。
しかし、私はそうではなかった。かけ値なしに嬉しかった。焼跡の二間しかないバラックの三畳間に、何しろ一年近くも無為に寝ていたのだ。あまり病人に理解があるとはいえない、働き者の両親と祖母にかこまれて、家庭での療養生活にはうんざりしていた。療養所に行けば、そこには同病相憐れむお仲間がいるはずである。少なくとも、健康者に囲まれたひとりぼっちの病人ではない―。
入所してみて、私の期待は十二分に報われた。世のなかには、こんなにも多勢の結核患者がいたのかと眼を見張った。自分がその一人だということを、しばらくは忘れるくらい、驚き、あきれたものである。長いあいだ悩まされた病人であることの劣等感は、ここではまったく無用であった。
(「夜の秋」)
B なーるほど。自宅療養というのも、辛いものなんだね。同じ病気でなければ理解し合えないこともあるだろうし、郷さんにとっては、療養所の生活のほうが生きやすかったのかぁ。
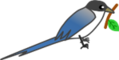
O 療養所のほうがいいという人は、郷ひとりではなかったようだよ。中には見る影もないほどやせ細って入所してきて、婚家に残してきた子を思って二晩泣き明し、その後数日昼も夜も眠り続けたのち食欲を取り戻し、ひと月もしないうちに別人のように太って若返った同室の患者もいたらしい。このとき郷は、彼女の婚家での療養生活を思って、その変貌ぶりを理解したって。郷にとって最初の療養所生活は、わりと快適なものだったようで、朝から晩まで好きな本を読み続けても「女のくせに」なんて言われずにすんでよかった、と後に振り返っている。
B そっか。心おきなく読書三昧だったんだね。
O 最初の療養所は、翌昭和22年には退所して、そのあとは群馬のお寺に預けられるんだ。療養と花嫁修業を兼ねて、ね。
B お寺で花嫁修業?!
O 一人娘でいずれはお婿さんを迎えて家を継ぐ身だったんだ。預けられた寺の住職は僧侶で俳人、夫人も俳人で茶道の師範。俳句やお茶を習いながら家事万端仕込まれるという段取りだった。でも、太宰治にあこがれる文学少女は、横浜の実家に帰って文学の勉強をしたいという気持ちが強くて、3~4年寺預かりのはずが、2年足らずで切り上げてしまうんだ。
B 花嫁修業より文学の勉強か。意志強固だな。
O 実家に帰ってから、就職口を見つけて夜間大学への入学を準備していた郷だったんだが、まもなく結核が再発してしまう。花嫁修業といいながら、実は寺でゆっくり療養を、という周囲の配慮だったのに、自分のわがままを通して早く切り上げた結果の再発だったから、このときの療養生活はとてもつらかったと振り返っているよ。
B う~ん、やっと社会復帰して、同時に文学の勉強も志したのに、再発かぁ~。。。この、つらかった療養って、まだ清瀬の前の話だよね。
O そう。まだ清瀬の前の療養。郷のエッセイを読んでいると、私立病院の結核病棟に入っていただけじゃなくて、自宅で療養した時期もあったらしい。いずれにしても、この時がいちばん苦しかったようだよ。
自殺しようと思ったことも、一度や二度ではなかった。その度に、偶然が実行を妨げたり、思い直させたりして、私は生きのびることができた。あのとき、ああいうことがなければ、死んでいたはずだ、と思い当たることがいくつかある。私が死なずにすんだのは、ひたすら運が強かったからだという気がする。
このときの療養生活は二三歳まで、四年近くつづいた。自殺を思いつめていないときは、本を読んだり、思いつくままにノートに何かを書き散らしたり、誰に読んでもらうあてもない小説を書いたりしていた。このころ書き始めたノートは、ずっと後になってから『色のない絵』というエッセー集になった。
(「不思議な力」)
B 自殺を思いつめるくらい苦しんだんだね…。読んでもらうあてもなく書くものに、どうにもならない想いをぶつけてたのかなぁ。『色のない絵』読んでみたいな。

O 『色のない絵』は、昭和50年に自由企画・出版というところから出された本だ。郷本人が「あとがき」でいわく、だいじなことを決めるとき、いつだって論理的だったためしがないが、25年も前に書いて、20年以上も埃にまみれて埋もれていたものを、なぜ今頃発表する気になったのか、自分でもよくわからない。自分の書いたものは焼いてしまうのが常なのに、この原稿はこれまでついに焼き捨てることのなかった唯一のものだから、愛着の深さをわかってほしいって。
B きれいな本だね。
O 1年区切りの章ごとに、とりどりの色の扉があしらわれていて、目を引くよ。その色扉をあけると、西暦年と郷の年齢が記されていて、文字通り色のない絵が添えられている。装丁・挿画は森秀男。その年の代表的なできごとも列挙されていて、どんな空気のなかで彼女が書いたのかがわかるのもいい。20歳から23歳までの4年間がそこにある。
B さっき、このときの療養生活は23歳まで4年近く続いたって言ってた、ちょうどその時間だね。
O この時期は彼女の人生で一番といっていいほど暗い時期だった。でも、見方を変えて、こんなふうにも書いているんだ。
(「不思議な力」)
B 郷さんって、強い人だね。
O 「 自分が見かけよりは、はるかにしたたかな人間であることを最初に発見したのも、この頃である」って。
B 戦争や結核の経験が人を強くしたのかな。石田波郷さんの『惜命』のときにも思ったけど、病気を抱えて辛いときも、療養所の時間を楽しむ工夫をして、何よりも、生きるんだ!という気持ちが強かった人が生き抜いたのかもしれないなあ。
O そうかもしれないね。ただ、そうは言っても病気が相手だからね。生きたいと願いながらも、どうすることもできなかった人もいた。想いだけではかなわないこともある。でも、病床にあって「書く」ということが心の支えになったところは、大きくあると思うよ。郷も、例えば日記は、「自らの心の屈折を解放するための手段として必要だった」と言っているし、日記に限らず「今までの生涯で一番たくさんかいたのは、結核の療養中であった」とも言っている。文章を書くには、書くべきできごとが多くあるということ以上に、もの思う心が必要なのだ、とね。
B もの思う心を持つだけの時間が、療養生活にはあった、ってことだね。その後、郷さんは?
O 結核の状態が安定してからは、野間宏(のま ひろし)の文学サークルに参加したり、日本文学学校という専門学校に入学したりして、本格的に文章修業をするんだ。昭和28年には『横浜文学』という同人誌に短編小説をいくつか発表して、のちに芥川賞を受賞する小説「れくいえむ」の構想を練り始めるんだけど、翌29年、再び結核が悪化。いよいよ清瀬の東京療養所に入ることになるんだ。
B おーーっ、清瀬! きたー。
O 続きは、またこんど。
B ええ~、いいところなのにぃ。「こんど」は、なるべく早く、ね!
O ギュイ~
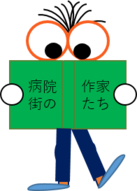
![]()
(引用)
郷 静子「古傷」『月刊保団連』225号(昭和60年8月号)
郷 静子「夜の秋」「不思議な力」『女の生きかた 主婦作家の日々』大月書店 1982年8月
郷 静子「思い出の看護婦さんたち」『看護』第33巻第7号(昭和56年6月)
(書影)
郷 静子『色のない絵』自由企画・出版 昭和50年6月(絶版)
![]()
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <郷 静子 3. 手術と職業訓練>
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】
![]()
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
