きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <郷 静子 3. 手術と職業訓練>

![]()
B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)
郷 静子 3. 手術と職業訓練
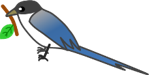
O ギュイ~ お待たせ、お待たせ。
B わぁい、よかった、よかった。郷さんの話の続きを聞きたかったんだよ。清瀬の東京療養所に入ることになった、っていうところまで聞いたんだ。いつ頃のことだったっけ?
O 東京療養所で手術を受けたのが、昭和30年。
B 昭和30年ってことは、吉行淳之介の手術より1年あとだね。郷さんも、肺に空洞を持っているのは文化的じゃない、っていうので切っちゃったの?
O 本人が書いているものがあるから紹介しよう。郷は10代の半ばから20代の半ば過ぎまで、十数年間、結核とつきあっている。
(「思い出の看護婦さんたち」)
B えええーっ、空洞のところだけじゃなくて、左の肺を、まるごと!取っちゃったってこと!?
O そう。
B 肺を取っちゃうなんて、信じられない! たしかに肺は右と左、2つあるけどさぁ。ひとつ取っちゃって、平気なもの、な、の?
O 反対側の肺に病巣がなくて、きれいな状態だったんだろうね。そうじゃなければ、できない手術だ。肺活量は減るけれど、折り合いをつけて生活することは、できる。
B へえ、そうなのか。郷さんは清瀬に、どのくらいいたの?
O 入退院の詳しい日付はわからないんだが、郷が東京療養所にいたのは、昭和30年から31年のようだ。自身が「最後の国立療養所では入院期間が長かった」と述べているから、過去2回の入院より長かったようだね。
B そうなんだね。大きな手術だったんだろうけど、十数年続いた結核との縁が切れたというのは、よかったね。さすが、清瀬の東京療養所ってことね。
O 名医がいたからね。手術を受けるなら清瀬で、と思ったのかもしれないね。
B 療養所での思い出とか、書いてないの?
O 療養所にいる時間が長かった分、出会った看護婦さんも多く、あ、当時は看護師さんのことを看護婦さんと言ったんだが、思い出す人も多いって。
私の好きな看護婦さんは、小柄で、知的な感じのするひとであった。無器用な私が、あるとき、缶詰をあけるのに缶切りがうまく使えなくて困っていたら、通りがかりにさっと手をのばしてスイスイと開けてくれた上に、缶切りの使い方も要領よく教えてくれた。また、秋の文化祭の写真展には、彼女の冬山登山の雄姿が大きく飾られて、改めて憧れ直したものだった。
(「思い出の看護婦さんたち」)
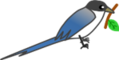
B 「いっせいに」っていうところが、大きな療養所の感じ、するよね。
O 東京療養所は1000床の大療養所だったからね。
B それにしても、文化祭!? 療養所のなかで!?
O そうだよ。文化祭は春と秋、開かれて、写真展だけじゃなく、演劇の上演があったり、文芸サークルは作品を掲示したり、いろいろな催しがあったようだ。
B 郷さんも、参加したかな。
O 出品したかどうかは、わからない。でも、見には行ったんだね。単調になりがちな療養生活のなかで、こういう催しものがあると、きっと励みになったり、慰めになったりしただろうね。
B なんか、楽しそうだな。
O そんなこんなで体調が回復した郷は、社会復帰に向けて、職業訓練を受けるんだ。
B へえ~、職業訓練!?
O 療養所にいて、長く社会から離れているし、結核が治っても、職場復帰や就職は、そう簡単なことではなかったんだよ。だからこそ、回復した人たちが、手に職つけるための職業訓練施設があった、というわけだ。清瀬のドクターたちは、早くからリハビリテーションに関心を寄せていたし、患者の回復は、単に病気を治すことだけじゃなく、社会復帰できてこそ治ったことになる、と考えていたからね。東京療養所には、回復期の患者が作業療法を行うなかで、社会復帰に向けて職業補導が受けられる付属施設もあったんだよ。
B 手に職、かぁ。
O 郷が取り組んだのは、謄写版の技術。それが東京療養所の付属施設でのことだったのか、直接の記述がないから確定できなくてもどかしいんだが、東京療養所付属の施設は薫風園といって、そこでの職業補導は謄写版の他に、時計修理、ラジオの組み立て、タイプライティング、写真技術、経理、興味深いところでは、細菌を検査する技師の養成、というのもあったんだよ。
B へええ、いろんなのがあったんだね。謄写版の技術って、例のガリ版印刷の技術でしょ?
O 郷の言うところの「孔版印刷」。職業訓練に努めるなかで、仕事を通じて知り合った人と郷は結婚するんだよ。
B おお、運命の出会いがそんなところにあるとは! ずっと結核と闘う日々だったから、結核が縁結びっていうのは、本当によかったね。
O そうだね。ただ、夫と出会った郷は、脱・文学少女を決心して、それから10年以上、筆を置くんだ。その間にふたりの子どもにも恵まれる。
B あれ? でも、郷さんは芥川賞小説家になるんだよね?
O 昭和43年に『横浜文学』の同人に復帰して、家事育児の合間に小説を書いたり、洋画をたしなんだり、余暇を楽しんでいたんだ。そういうとき、「第4次防衛力整備計画」が発表される。日本の軍備が増強されていくことに不安を覚えた郷は、自身の戦争体験を伝える必要を感じて一念発起するんだ。
B ほお。
O 清瀬での療養生活に入る前に構想を練っていた「れくえいむ」を、昭和47年に書き上げて『横浜文学』に発表すると、作品が評価されて同じ年の大手文学雑誌『文学界』12月号に掲載されるんだ。
B たしか、「れくいえむ」の構想を練り始めたのは、昭和28年だったよね。ということは、完成まで約20年!すごいな。ところで「れくいえむ」って、どういうお話なの?
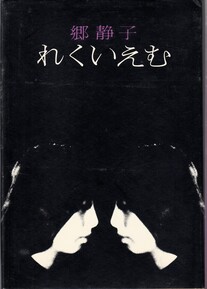
O 「れくいえむ」は、戦時中を舞台にした作品で、主人公の節子は、女学生なんだ。勤労動員のなかで結核になるんだが、療養を拒否して、ひたすら真空管づくりの作業に身を挺するんだが、空襲で父も母も喪い、兄も戦死してしまう。節子の結核も、戦中戦後の劣悪な環境のなかで悪化、一人暮らしの焼け跡の壕のなかで虚しく死んでしまう、というのが主なプロット。
B 暗い、ね…
O 作品の特徴は、重要な登場人物が皆、死んでしまうという点にある。とにかく、女学生のピュアな眼を通して戦争の悲劇が描かれていく。節子の語りによって、また、鳩野高等女学校の友人なおみとの交換ノートの文面によって、ね。戦争に駆り出されていく兄、その友人たち、動員先の工場で出会った青年、空襲の現実、父親の学説から非国民のレッテルを貼られたなおみの家族の孤独、ついに血痰を吐いてしまう節子の動揺と諦観…
B 郷さんの戦争体験の反映なの?戦争経験者だからこそ、戦争の悲惨さを後世に伝えなくてはと思ったのかな。軍国少女だったという郷さんだからこその執筆動機なのか。こりゃ、暗いとかなんとかって問題じゃないな。読んでみるよ。
O そして翌昭和48年、郷はこの作品「れくいえむ」で芥川賞を受賞するんだ。小説としては未熟な点もあるという評価ではあったんだが、反戦という切実なテーマが強く伝わる作品というところに芥川賞が与えられたようだよ。
B ひゅう、芥川賞! すごいじゃん。清瀬の病院街で過ごした作家で、吉行に続いて2人目の芥川賞!めでたい。
O 吉行と郷と芥川賞ということに関して言うと、郷が受賞したとき、吉行淳之介は芥川賞の選考委員に名を連ねていたんだよ。
B え?じゃ、吉行は「れくいえむ」を読んで、受賞していい、とかなんとか、言ったわけ?
O そう。「戦争にたいする見方も納得できて、親愛感をもったが、私自身の体験や想像を上まわる部分がなく、ギョッとさせられるところがないのが物足らなかった」と、やや厳しい選評を与えている。同じように戦争も結核も経験した吉行にとっては、あまり新鮮さが感じられなかったのかもしれないね。
B でも、芥川賞を受賞したんだから、郷さんはそれからバンバン、小説を発表したんでしょ?
O ところが、郷の発表した小説は、多くない。あくまでも、自分のペースで書きたいことを書いていたんじゃないかな。
B 結核のことは、書いてないの?
O 『小さな海と空』という作品がある。主人公は、結核を病んで、療養所で過ごす女性なんだ。
B おおっ、来ましたねー
O 気になるかい?続きは回を改めて、ゆっくり話そうね。
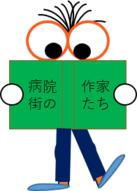
![]()
(引用)
郷 静子「思い出の看護婦さんたち」『看護』第33巻第7号(昭和56年6月)
(書影)
郷 静子『れくいえむ』文藝春秋 昭和48年
![]()
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <郷 静子 4.「小さな海と空」>
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】
![]()
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
