きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <藤井重夫 4. 映画『風立ちぬ』に怒る>

![]()
B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)
藤井重夫 4. 映画『風立ちぬ』に怒る
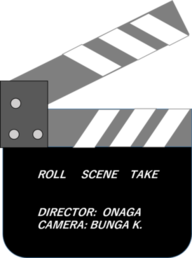
O 藤井重夫は、朝日新聞社時代から映画評論で活躍していたという話、覚えているかな。
B うん、覚えてるよ。新聞だけじゃなくて、雑誌にも記事をかいていたし、講座までやってたんだよね。
O その藤井が、とある映画について、書かずにいられなかった強い思いのこもった評論を残しているんだ。
B おや、それは何の映画?
O 『風立ちぬ』だよ。
B 『風立ちぬ』! 福永さんのお話のとき、ぼくがアニメの映画のこと?ってきいたら、もともとは堀辰雄っていう人の小説で、その堀さんは福永武彦が師匠と慕った人だよ、って教えてもらったんだ。
O そうだったね。藤井が見たのは昭和29年の映画で、やはりアニメではなかった。ヒロイン役は久我美子、父親役は山村聡、恋人役は石浜朗と、名だたる俳優たちが出演している。監督の島耕二は、『風の又三郎』や『金色夜叉』といった文学作品も映画化している人だ。映画『風立ちぬ』の原作は、堀辰雄の同名小説。藤井によると、映画は、島監督が堀の原作を「任意に脚色して作った」ものなんだが、結核患者の実際を、なにもわかっていない!「ウソをウソのまゝなまで出すとき、その小説や映画や芝居は、ウソになる」と藤井は酷評している。
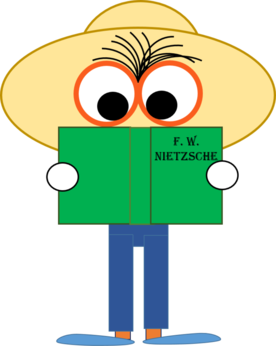
B 怒ってるねー。だけど、どうしてまた、そんなに腹を立てたの?
O 怒りその1. まず、「冒頭シーンから、この映画はウソを描いている」。映画の冒頭、ヒロインは軽井沢の高原の草原に画架を立てて絵を描いている。結核の療養で高原に来ているはずのヒロインが、帽子もかぶらず直射日光にさらされるままでいるとは、なにごとか。
B 太陽の光がよくないの?紫外線とか?
O そうなんだ。日光は、浴びる量が病状に合ったものなら、一つの刺激になりプラスにもなるけれど、長く浴びて刺激が強すぎると、疲れが増したり、病状によっては発熱や喀血を招いたりする。紫外線は波長が短くてよく反射するから、日かげにいても、そうとう浴びているんだよ。だから、清瀬の療養所の患者たちは、外に出るときはみな麦わら帽子をかぶっている。よそゆきの服装の年ごろの娘たちだって、頭には日に焼けた古い麦わら帽子。日光を頭から受けないために男も女も外に出るときは麦わら帽子、あるいは手ぬぐい、タオルを頭に頂く。冬のさなかに雪だるまを作るときですら、である。
B ほお。
O 映画をつくるときに、関係者が一度でも清瀬に来ていれば気がつくことなのに、リサーチが足りない。そもそも、結核について知ろうという気があったのか。
B うーーん。
O 藤井の怒りその2.ヒロインは重い絵の道具を携えて移動している。病人はエネルギーの消費を極力避けて、菌の活動を手助けすることのないようにしなければならない。
B なるほど。
O 藤井の怒りその3.父の姿を遠くからみとめ、重い道具を持って駆け出すとはなにごとか。しかも、遠くから「お父さーん」と叫ぶなど、言語道断。肺に負担をかけないように、なるべくしゃべらないようにする沈黙療法すらあるというのに。生きている限り肺は絶え間なく働いている、その肺を結核菌がむしばんで弱っているというのに、走ったり大声を出したりしていらぬ負担をかけるとは患者の道にあらず。
B 怒ってるー
O 怒りその4.健康な者でも歩きにくい山道を結核患者が無理に行くとはなにごとか。さもありなん、ヒロインは途中でへたばってしまい、そのあと病状よろしくなく、画面は自宅療養のシーンに転じる。
怒りその5.結核で寝ているというのに、ヒロインは一度も熱を測らない。検温は、結核患者にとって「三度の食事以上に不可欠な自診法」であるのに。こういうディテールを無視しすぎている。
怒りその6.医者役の池辺良は、レントゲン写真を見ることもなく、診察をするでもなく、初対面の恋人からちょっと病状をきいただけで簡単に薬を処方してしまう。結核専門医にあるまじき行為。
B ひええ~ 次から次に…
O 怒りその7.薬の名前を恋人から電話できいた父親は、「娘よろこべ、この薬でお前の病気はすぐ治るぞと喜ぶ」。
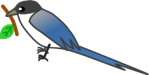
B めんような話、って?
O そうだな、不思議な話というか、奇妙な話というか。
B ヘンなの!ってことだね。ねえ、テーベって、結核のことだよね。
O そう。結核は英語で tuberculosis ドイツ語でTuberkulose 略してTB これをドイツ語の音で読むと「テーベー」。むかし、お医者さんが使うのはドイツ語だったからね。
さて、映画のほうでは「迷医」の処方による薬がたちまち効を奏し、何日目か、映画では説明がないものの、ヒロインは早々と床を離れて炊事を手伝ったり廊下をうろうろしたり。。。藤井はもうガマンできなくなって途中で映画館を出てしまう。
この映画が公開された昭和29年の5月には、藤井はまだ清瀬で療養中で、半年過ぎて退院後にようやく見に行ったというのに。
B あっりゃあ~それは、ざんねん。
O 怒りその8.
B え?まだある!
O 映画を全部見た人の話では、最後にヒロインは恋人とキスするという。
B キ、キ、キ、・・・
O「慄然、まことにあいた口がふさがらぬ」と藤井。
当時、一本の映画の観客数は平均4~500万人と言われたんだが、映画『風立ちぬ』はその平均を上回るヒット作だ。
B わお、ひらがなに怒りがこもってる!
O 藤井自身の結核は発見も早かったから一度の手術で治ったし、療養生活もあまり長くなくてすんだけれど、その陰には、結核を科学的に理解して、刺激を避けて真剣に療養していた姿があったということだろう。だから、影響力の大きな映画で無理解な描かれ方がされるのを見て、黙っていられなかったんだろうね。昭和29年といえば、進んだ手術ができるようになり、効果のある薬が使えるようになった時期ではあるけれど、結核は不治の病ではなくなったと言っても、治ったあとの社会復帰のハードルはまだまだ高くて、新しい課題が見えていた時代でもある。それに、療養所にたどり着くまでに症状が進んでしまっていて、長くながく結核と向き合いながらなお、治る希望を持ちにくかった患者もいた、そういう姿も見ただろう。
B 見てきたものと、映画で見たものが、あまりに違っていたんだね。怒る気持ち、わかる気がするよ。藤井重夫はこの映画評論や『千羽鶴の祈り』を残していて、同じころ清瀬にいて手術の前に励ましあった吉行淳之介は『漂う部屋』に療養生活のいろんなシーンを書き込んでいて、いろんな人が書いたものを読み比べてみると、ひとつだけ読んだときよりいろんなことがわかる気がする。もっとほかにも、清瀬で結核療養して文章を残した人、いるの?
O いるとも。詩人も、小説家も、俳句や短歌の人もいる。プロの書き手もいるけれど、仲間との同人誌に書いた人たちもいて、それぞれに味わい深いんだ。引き続きどんどん紹介していこうね。お楽しみに。
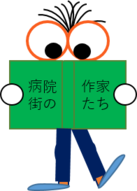
![]()
(引用)
藤井重夫「映画、それはときに“社会的凶器”となる」『映画評論』昭和30年2月号
(参考)
村田純一郎「結核患者と日光」『保険同人』昭和36年7月号
![]()
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【福永武彦(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【結城昌治(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【郷 静子(東京療養所)編】
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【吉行淳之介(清瀬病院)編】
![]()
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
