きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <山田文男 3. 秋櫻子 波郷 山田文男を語る>

![]()
B ブンガくん O 樹の上の声(オナガ)
山田文男 3. 秋櫻子 波郷 山田文男を語る
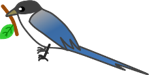
O 山田文男の『林の花』では、句のみならず注目すべきところがあるんだ。
B へえ、それはどういうところ?
O まず、水原秋櫻子による「序」。
B 秋櫻子さんは山田さんの先生だね!
O そう。『林の花』に寄せられた序文によって、山田文男の身の上や句集の成り立ちがわかる。
山田は、戦後「馬酔木(あしび)」が復活した当時の馬酔木集の主要な作者だったという。親戚縁者もほとんどなく、身ひとつというような境涯だったとも。
やうやく長い療養も了り、しづかな家庭もできて、君にも春がめぐつてきた。これもまことに素朴な春である。さうしてそのたのしさの中に、多くの人々の友情によつてこの句集が出来あがつた。傍で見てゐても心のあたゝまる思ひであつた。
(水原秋櫻子「序」『林の花』)
B いいね、いいね!
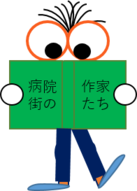
O さて、この『林の花』という題名だけど、名付けたのは誰だと思う?
B 清瀬病院の俳句の仲間、かな?
O 句集の後記で、お世話になった先生方にお礼を言うなかで、山田はこう書いている。
(山田文男「後記」『林の花』)
B 波郷さんがつけた題名だったんだね!
O ふたたび秋櫻子の「序」の文を引いておこう。
(水原秋櫻子「序」『林の花』)
B そっかぁ、ぴったり!の名前なんだ。山田さんは、波郷さんにも秋櫻子先生にも、だいじにしてもらっていたんだね。
O 『林の花』刊行にあたっては多くの人が賛同して支えたようだ。山田は句集の後記で、お世話になった先生方だけでなく、蔭ながら温かく見守ってくれた人たちにもていねいに溢れんばかりの感謝を記しているんだ。その中には刊行会の事務を担当した中山良章や変わらぬ友情の古賀まり子の名前もあるし、「常に善意と友愛の持主であつた療養所の療友達」も含まれる。
B なんか、山田さんのそういう誠実さに皆が惹かれていたのかも。そんな気がする。
O そうかもしれないね。題名を寄せた波郷は、『林の花』の跋(ばつ)のなかで、
B え?バツ??
O 跋文。書物の終わりに書く文章のことだよ。波郷は、「草木瓜(くさぼけ)や故郷の如き療養所」という自身の句を引いて、山田文男の『林の花』をひもとくと、この句を思い出し、療養生活がなつかしく心に浮かんでくると言っている。波郷が最初に清瀬の東京療養所で過ごした歳月は2年に満たなかったが、それは死とたたかった歳月であって、変化に富んだはげしい歳月だった。その思いが山田の十余年の療養生活を畏敬の眼をもって眺めさせると言うんだ。「林の花」はそういう歳月を詠み込んだ句集だ、と。
B 生きることと死がすぐ隣にあった日々のことが、激しい言葉じゃなくて静かに詠まれていて、同じように療養生活を送った人にはたまらなく響くんだろうね。
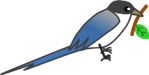
O 波郷は同じ跋文のなかで、療養俳句の特殊な「場」について触れている。正岡子規(まさおか しき)以来、療養俳句の歴史は短いとは言えないかもしれないが、波郷の『惜命(しゃくみょう)』の出現で独自世界を打ち立てたとするのは誤りであると。
B そうなの?
O 子規も、戦後の石橋秀野(いしばし ひでの)らも、大部分の闘病句は療養所ではなく家庭で詠まれているが、はげしい病勢の進行が作者の生命を究極に駆り立てたのだという。それに比べると療養所の生活は多くが数年あるいは十数年に及び、その間ずっと闘病に緊張した精神状態が続くのではなく、多くの時間はむしろ、生活の空白感、無為感とのやりきれないたたかいだ、というんだ。
B 山田さんは清瀬病院でそういう時間を過ごしたからこそ、死ななかった自分にできることは、たくさんの亡くなった友達を思い、いま病気で寝ている友達の心が安らかであるように祈ることだ、って言ったんだね。それって、すごいことだよね。
O 波郷の跋文の続きを引いておこう。
山田文男氏は、ながい療養生活をした人特有の、寡黙でひかえ目な挙措で目立つ人である。大勢の人と一緒にいると何處にいるのかわからない。それでいて山田氏の見えぬことが気になつて目を配らずにいられなくなるような人である。山田氏の句風も亦そういうところがある。私はこの跋文では山田氏の句風について吹聴することをさしひかえたい。然し読者は、このひかえ目で静かな句の底にはげしい生命詠唱のひびきを読みとることができる筈である。
(石田波郷「跋」『林の花』)
B 波郷さんの文章を読んでると、山田文男さんがどういう人だったのかわかる、っていうか、なんだか知っている人のような気がしてくるね。
O 山田文男が清瀬病院で俳句に出会った昭和17年から、途中の疎開時期をはさんで再入院して32年に退院するまでの間に、結核医療のようすはとても大きく変わっているんだ。薬が使えるようになったし、外科手術も進化して、結核は不治の病から治る病気になっていく。
そうした変化は療養俳句にも影響しないわけないと思わないかい?波郷の跋文の結びはこうだ。
(石田波郷「跋」『林の花』)
B 「誠実に生きぬいた生命の歌」かぁ。ぼく、もういちど『林の花』をゆっくり読んでみるね。
O 『林の花』誕生の舞台、清瀬病院の姿を紹介しておこう。昭和31年秋に出された『開院二十五周年記念誌』に載っている病院の全景写真だ。正確にいうと国立療養所清瀬病院。右下に西武池袋線の電車が写っているのが見えるかな。中央に大きく写っているのが清瀬病院の建物。上の方に写っている一列の病棟は、都立清瀬小児療養所、のちの清瀬小児病院だよ。
B 山田さんの句に登場する、夕暮れに見えた「産院」でしょ。それにしても清瀬病院って、大きな病院だったんだね。ここで、山田さんも、古賀さんも、中山さんも、吉行さんも……いろんな人がいろんな思いで過ごしたんだね。

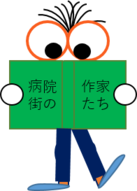
![]()
(引用・参考)
山田文男『林の花』昭和34年2月 近藤書店より
水原秋櫻子「序」
石田波郷「跋」
山田文男「後記」
(写真)
「本院の航空写真」『開院二十五周年記念誌』国立療養所清瀬病院 昭和31年(1956)10月20日
![]()
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <山田文男 1. 府立清瀬病院で俳句に出会う>
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 <山田文男 2. 句集『林の花』>
- きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩 【石田波郷(東京療養所)編】
- 清瀬と結核
![]()
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
