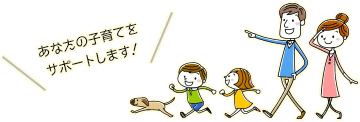定期予防接種
予防接種は、感染症による様々な病気を予防することを目的に行われます。
定期予防接種は、予防接種法で定められた予防接種で、小児を対象とする予防接種は保護者に接種の努力義務が課せられています。また、定期予防接種は接種方法、接種時期、接種間隔等が決まっています。
定期予防接種を受ける際には、生後2か月になる月の前月の下旬から当月の初旬に送付する予診票と一緒にお渡ししている冊子「予防接種と子どもの健康」等をよく読み、接種の必要性や副反応等のリスクについて理解したうえで接種してください。また、清瀬市の予診票と母子健康手帳を必ずご持参ください。
任意予防接種は、個人が接種するかどうかを選択し、希望者が各自で受けるものです。清瀬市では、任意予防接種のうち接種費用の助成を行っている予防接種があります。
子どもの予防接種一覧
子どもの定期および任意予防接種の一覧は、下記「子どもの定期・任意予防接種一覧」をご覧ください。子どもの予防接種の種類や対象者等をご確認いただけます。
清瀬市の予診票
清瀬市民として定期および任意予防接種を実施する場合、清瀬市の予診票が必要です。予診票の送付時期や送付方法は、予防接種の種類ごとに異なります。詳しくは、上記「子どもの定期・任意予防接種一覧」をご覧ください。
なお、転入・紛失等による予診票の発行は、原則、母子健康手帳の接種歴をもとに実施しております。
母子健康手帳の紛失等で接種歴が分からない場合は、過去に住民登録があった自治体やかかりつけの医療機関等で、接種歴が再発行できるかどうかお問合せください。接種歴が無い状態で接種し、接種後に過去に接種していたことが判明した場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されない場合があるため、可能な限り接種歴は明確にして下さい。
どうしても接種歴が分からない場合は、接種対象者および保護者(接種対象者が成年または既婚者の場合は本人のみ)の身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえで、子育て支援課母子保健係へお越しください。なお、清瀬市の予診票を使用して5年以内に接種した接種歴は、子育て支援課母子保健係で再発行することができます。詳しくは、下記「予防接種の接種歴」をご確認ください。
清瀬市に転入した場合
母子健康手帳をお持ちのうえ、子育て支援課母子保健係へお越しください。接種期間や実施医療機関等の予防接種に関する説明と、転入時点で必要な予診票をお渡しをいたします。お越しいただくことが困難な場合は、下記電子申請や郵送申請をご利用ください。
また、転入前の自治体が発行している予診票は、清瀬市に住民登録をした後は使用できません。お持ちの方は、ご自身で破棄をしてください。なお、母子健康手帳や「予防接種と子どもの健康」は、転入後も引き続きご利用いただけますので、大切に保管してください。
予診票を紛失した場合
予診票がお手元にない方は、予診票の再発行を行います。以下の方法で予診票の発行をお申し込みください。
- 窓口申請(即日発行)
- 電子申請(後日郵送)
- 郵送申請(後日郵送)
※電子および郵送申請の場合、予診票がご自宅に届くまでに1~2週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口にお越しください。
窓口申請
母子健康手帳をお持ちのうえ子育て支援課母子保健係へお越しください。接種歴等を確認した後、必要な予診票をその場でお渡しします。
なお、本人あるいは保護者が特段の理由で申請ができない場合、本人あるいは保護者からの「委任状」により、保護者以外の方が代理で申請をすることができます。詳しくは、下記「委任状・同意書」をご確認ください。
電子申請
下記URLより、「子どもの定期予防接種予診票 交付・再交付申請」の申請フォームを開き、必要事項をご入力の上で申請してください。その際、母子健康手帳の出生届出済証明のページ及び全ての予防接種の接種歴のページの画像データ(スマートフォンで撮影したもの等)をアップロードしてください。また、入力情報はお間違いのないようにご留意ください。
申請内容の確認後、順次郵送にて予診票をお送りいたします。予診票がお手元に届くまで、1~2週間程度かかります。
郵送申請
下記の関連ファイル「定期予防接種予診票交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。そして、必要書類を同封の上で下記送付先へご郵送ください。
子育て支援課母子保健係に到着後、申請内容を確認し、順次郵送にて予診票をお送りいたします。予診票がお手元に届くまで、1~2週間程度かかります。
※申請書がダウンロードできない方は、お問合せください。
必要書類
- 定期予防接種予診票交付・再交付申請書
- 母子健康手帳の出生届出済証明のページのコピー
- 母子健康手帳の予防接種の接種歴のコピー(全て)
送付先
〒204-8511
東京都清瀬市中里五丁目842番地
清瀬市福祉子ども部子育て支援課母子保健係 宛
清瀬市から転出した場合
清瀬市の予診票は、清瀬市に住民登録が無い方は使用できません。清瀬市から転出した方は、清瀬市の予診票は破棄をして、新たに住民登録をした自治体で予診票の発行手続きを行ってください。
予防接種の接種歴
定期および任意予防接種の接種歴について、清瀬市の予診票を使用して5年以内に接種した接種歴は再発行することができます。ご希望の方は、接種対象者および保護者(接種対象者が成年または既婚者の場合は本人のみ)の身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえで、子育て支援課母子保健係へお越しください。なお、予防接種法において、予防接種の接種歴は5年間適正に管理・保存することとされているため、5年を超過した接種歴は再発行できない場合があります。また、予防接種の接種歴は、個人情報に該当するため、お電話でお伝えすることはできません。
ワクチンの在庫状況
定期・任意予防接種におけるワクチンの在庫状況につきましては、実施医療機関にお問合せください。なお、全国的なワクチンの供給状況につきましては、下記関連リンク「ワクチンの供給状況について(厚生労働省)」をご確認ください。
四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について
現在、四種混合ワクチンの販売が中止されている影響で、清瀬市内の一部医療機関より四種混合ワクチンの在庫が不足しているという情報が入っております。まだ四種混合ワクチン全4回の接種が完了していない方は、四種混合ワクチン(初回3回+追加1回)及びヒブワクチン(初回3回+追加1回)の残りの接種回数に応じて、下記の方法で接種を完了することを推奨いたします。なお、下記の各表は一例です。
(1)既に接種した回数が四種混合ワクチン=ヒブワクチンの場合
| 既に接種したワクチンとその回数 | これから接種するワクチンとその回数 | ||
|---|---|---|---|
| 四種混合ワクチン | ヒブワクチン | 五種混合ワクチン | |
| 初回1回目、初回2回目 | 初回1回目、初回2回目 | 初回3回目、追加1回 | |
| 初回1回目、初回2回目、初回3回目 | 初回1回目、初回2回目、初回3回目 | 追加1回 | |
(2)既に接種した回数が四種混合ワクチン>ヒブワクチンの場合
| 既に接種したワクチンとその回数 | これから接種するワクチンとその回数 | ||
|---|---|---|---|
| 四種混合ワクチン | ヒブワクチン | 五種混合ワクチン | ヒブワクチン |
| 初回1回目、初回2回目 | 初回1回目 |
初回3回目、追加1回 |
初回2回目 |
| 初回1回目、初回2回目、初回3回目 | 初回1回目 | 追加1回 | 初回2回目、初回3回目 |
(3)既に接種した回数が四種混合ワクチン<ヒブワクチンの場合
| 既に接種したワクチンとその回数 | これから接種するワクチンとその回数 | ||
|---|---|---|---|
| 四種混合ワクチン | ヒブワクチン | 四種混合ワクチン(または、五種混合ワクチンあるいは三種混合ワクチン+不活化ポリオワクチン) | 五種混合ワクチン |
| 初回1回目 | 初回1回目、初回2回目 | 初回2回目 | 初回3回目、追加1回 |
| 初回1回目 | 初回1回目、初回2回目、初回3回目 | 初回2回目、初回3回目 | 追加1回 |
(3)のケースについて
- 四種混合ワクチンについては、今後さらなる在庫不足が想定されることから、事前に市内または近隣11市内(立川・昭島・東村山・小金井・小平・国分寺・国立・狛江・東大和・武蔵村山・東久留米)の実施医療機関に在庫状況を問い合わせいただくことをおすすめいたします。
- 四種混合ワクチンの代替として五種混合ワクチンあるいは三種混合ワクチン+不活化ポリオワクチンにて接種いただくことも可能です。
五種混合ワクチンで接種をする場合、ヒブワクチンの成分が規定の接種回数分を超過することとなります。この点について、厚生労働省は安全面等に関する「科学的知見が明らかになっていない」との見解を示しているため、接種医から十分な説明を受けてから接種をご検討ください。
また、三種混合ワクチンは、百日咳流行の影響を受け、現在限定出荷の状況にあります。今後、四種混合ワクチンと同様に在庫不足が懸念されるため、三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンで接種する場合は、予約時に各ワクチンの在庫状況をご確認いただくことをおすすめいたします。 - 定期予防接種実施医療機関の一覧は、下記関連リンク「子どもの定期予防接種実施医療機関」からご確認いただけます。
予診票の差し替えについて
- 間違い接種を防止するため、交互接種をする際は原則予診票の差し替えが必要となります。ただし、四種混合ワクチンから五種混合ワクチンに切り替えて接種する場合に限り、四種混合ワクチンの予診票を使用して五種混合ワクチンを接種していただいても差し支えございません。その際、ヒブワクチンの予診票は、ご自身で破棄していただきますようお願いいたします。なお、引き続き四種混合ワクチンの予診票を五種混合ワクチンの予診票に差し替えてから接種することも可能です。
- 三種混合ワクチン、不活化ポリオワクチンの予診票は、上記「予診票を紛失した場合」と同様の方法でお渡しいたします。お手数をおかけしますが、接種の前に発行申請をしていただきますようお願いいたします。
- 子どもの定期予防接種実施医療機関
-
四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項について(令和7年7月25日付事務連絡) (PDF 61.0 KB)

-
四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について(令和7年2月27日付事務連絡) (PDF 171.3 KB)

-
百日せきの流行状況等を踏まえた、定期の予防接種の実施及び 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの安定供給に係る対応について(令和7年5月19日付通知) (PDF 211.6 KB)

予防接種における年齢と接種間隔の数え方
年齢の数え方
「~歳以上」という場合は、お誕生日の前日から接種が可能です。また、「~歳未満」「~歳に達するまで」「~歳に至るまで」という場合は、いずれも「~歳の誕生日の前日まで」に接種します。
(例1)
平成20年4月2日生まれの方が「生後3月から生後90か月に至るまでの間にある方」となるのはいつからいつまでか。
⇒平成20年7月1日から平成27年10月1日まで
【考え方】
「生後3月から」=「生後3か月のお誕生日の前日から」=「平成20年7月1日から」
「生後90月に至るまで」=「生後7歳半になるお誕生日の前日まで」=「平成27年10月1日まで」
(例2)
平成20年4月2日生まれの方が「9歳以上13歳未満の方」となるのはいつからいつまでか。
⇒平成29年4月1日から令和3年4月1日まで(9歳のお誕生日の前日から13歳のお誕生日の前日まで)
接種間隔の数え方
「~日以上の間隔をおいて」という場合、接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。例えば、4月1日に接種をした場合、「1日以上の間隔をおいた日」は4月2日を間にはさんだ4月3日です。
6日以上の間隔をおく=接種した一週間後の同じ曜日から接種できます。
27日以上の間隔をおく=4週間後の同じ曜日から接種できます。
(例)
平成25年4月1日に接種した場合、「20日から56日までの間隔をおいて接種」は、いつからいつまでか。
⇒平成25年4月22日から平成25年5月28日が接種期間となります。
異なる予防接種の接種間隔
種類の異なる予防接種の接種間隔については、下記の関連ファイル「異なる予防接種の接種間隔」をご覧ください。
副反応と健康被害救済制度
予防接種を受けた後、ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・はれ、しこり、発疹等が比較的高い頻度で認められます。通常、数日以内に自然に治りますのでご心配いただく必要はありません。
しかし、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけ等の症状があったら、医師の診察をうけてください。ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に一人程度)に脳炎や神経障害等の重い副反応が生じることもあります。その場合、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
詳しくは、厚生労働省ウェブサイト「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課母子保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2077
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。