中里(なかざと)
中里ぶらり
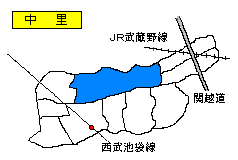
市のほぼ中央部に位置し、西部から北部にかけては川沿いに続く雑木林のグリーンラインが見られる、緑と住宅が調和した地域です。
また清瀬市の自然を語るうえでもっとも貴重なエリアで、四季折々に可憐な野草が花を咲かせ、野鳥の種類も数多く観察できます。
またこの地域は、豊富な自然とともに文化遺産が先人から多く受け継がれている地域でもあります。
清瀬金山緑地公園
清瀬金山緑地公園は、昭和61年に開設されました。広さは1.8ヘクタールあります。
武蔵野の風と光をテーマにした園内には、ケヤキ、クスノキ、コナラ、エゴノキ・ウツギ・ヤマハギなど樹木約9800本の株とクマザサ・各種野草が植えられているほか、公園入口付近にはパーゴラ(日陰棚)、小川の辺には、かわらぶきの東屋があります。また滝から落ちる水が小川となって流れ、その小川が園内中央部に広がる池に注ぎ込み、その湿地帯には、花菖蒲が顔を出し、行き交う人の目を楽しませてくれます。池の中央には、”柳”をデザインした噴水があり、独特な水の動きは、自然の安らぎを感じさせます。
その他にも昭和63年10月に新潟県朝日村(注)との姉妹都市提携が行われた記念として時計塔”窓”が建てられ、両市村の交流のシンボルとなっています。
注:平成20年4月1日、朝日村は合併し村上市となり、姉妹都市は解消されました。
中里万作:市指定無形民俗文化財
一説には、寛政の頃(江戸時代後期)に伝えられたといわれていますが、古老の話では、明治の初めに久留米村から習ったともいわれています。
出し物は白桝粉屋、日蓮記、広大寺の本尊の場、同茶屋場、日高川の道行の場、同船頭場、細田の奴、三人奴などがあり、明治初期の素人芝居としてこの地に伝わり、毎年4月28日の氷川神社の例大祭で保存会の人々によって演じられていましたが、現在は休止中です。
中里の富士塚
この富士塚は、富士山を信仰する人々の集まりである富士講によって築かれ、文政8年(1825年)に再築されたものと伝えられていますが、この富士塚は人力で土を積み上げてつくられたお山です。
明治7年(1874年)には、7尺5寸(約2m25㎝)高くしたと記録されており、高さが約10mとなり、現在の姿となりました。山梨県富士吉田から登山する北口登山道に祀られている神仏を全てそなえ、信仰の対象としての富士山を今に伝える富士塚です。都の有形民俗文化財に指定されています。
中里の火の花祭り
毎年9月1日に行われる中里の火の花祭りは、鳥居をくぐった富士塚の前に富士山をかたどった麦わらを積み上げ、登山道には108本のロウソクが立てられ、浄衣に身を固めた先達を先頭に山頂で「お伝え」と呼ばれる経文を唱えます。
下山の後、麦わらに火がつけられ、集まった人々は猛火にあたり身を清めます。その灰を門口に撒くと魔除けになるといわれています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41
電話番号(直通):042-493-8585
電話番号(代表):042-493-8585
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
