市史編さん草子「市史で候」 二十九の巻 「稲荷のかいだん」
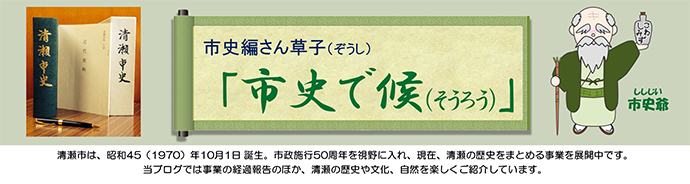
二十九の巻:「稲荷のかいだん」【平成28年8月12日更新】
夏といえば「かいだん」ですね。
そこで今回の「市史で候」も、「かいだん」を一つ……。

これはね、ついこの間、私が体験した話なんですがね。
下宿二丁目にある上宮稲荷神社ってお分かりになりますかね?
旭が丘交番の道向かいの、清瀬稲荷児童遊園の中にある、お稲荷さん。
お稲荷さんには西側からもいけるんですが、正面からお参りしようと思うと、南側の柳瀬川通りから石段を登ることになるんです。
急だな~、やだな~と思いながら、かなり急な石段を登っていく。
そうすると、ちょっとスペースがあって、また3段ほどの緩やかな石段があるんですよ。
あれ?なんで二つに分かれてるんだ?
そう思って足元を見ると、急な石段の、一番上の段の脇に小さな石の柱が建ってる。
どうやら、石段の始まりと終わり、左右両方、計4か所に柱が建ってるみたいなんです。
その内のひとつ、一番上の段の、神社に向かって右の柱。
よぉーく見ると、その柱、どうも文字が刻んであるらしい。
かがんで顔を近づけると、今度ははっきり読める。
「昭和九年三月」
へぇ、古いんだなぁって、思うじゃないですか。
それで、何の気なしに、3段しかない石段をみたら、こっちもやっぱり4つの柱が建ってる。
それじゃあ、同じことが書いてあるのかな、なんて、一番上の段、右側の柱を覗き込んだら……違うんですよ。
こっちは、昭和9年じゃないんですよ。
「嘉永三戌年十一月吉日」
嘉永3年、戌年だった年の11月って刻んである。
嘉永3年って、西暦でいえば1850年。
ペリーさんが浦賀に来たのが1853年だから、それよりも3年も前ですよ。
そんな昔から、石段の、少なくとも柱の部分はお参りに来る人たちを見つめてたんだなって思うと、なんだか背筋がスッとしちゃいましたね……。
と、いうわけで、今回は怪談ならぬ階段のお話でした。
舞台は、下宿二丁目の清瀬稲荷児童遊園。
児童遊園の中には、上宮稲荷神社があります。
そのお稲荷さんへの参道になっているのが、柳瀬川通りから登る石の階段、石段です。


改めてその石段を見てみましょう。

この写真では、急な石段だけで、その先にある3段の石段は見えません。

2つの石段には、それぞれ4つの小さな石の柱が建っています。

先ほどお話した通り、急な石段の柱には昭和9(1934)年3月と刻まれています。
これは80年以上前と古いように思えますが、3段だけの石段の柱には嘉永3(1850)年11月の文字。
江戸時代と更に古く、なんと150年以上も前でした。
3段だけの石段は、よく見ると、柱から続く石段の脇の石と、実際に足で踏む段の部分の石の色合いが異なります。
石材が違うのか、或いは、年代が異なるのかもしれません。
しかし、少なくとも柱は、150年以上前のペリーが浦賀に来航した頃から、歴史を重ねてきたのです。
普段気に留めていなかったようなものの中にも、長い歴史を持つものが隠れています。
そんなものを見つけたら、是非、市史編さん室までご一報を。
市史編さん室からのお願い
ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。
清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。
ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。
投稿おまちしております。
注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。
お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
